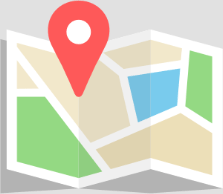(承前)千代田区長の石川雅己は都立大(現・首都大学東京)法経学部を経て、1963年に東京都庁に入庁した。そのため、石川と山田慶一は「都議会のドン」と呼ばれる内田茂と関係が深いとされている。
現在は練馬区長である前川燿男も、山田が「顧問」の名刺を持つ大都市センターで代表取締役を務めていた。そもそも前川も元都知事本局長などを歴任した都職員。そして山田との繋がりは内田茂都議との縁だと仄めかしていた。
■―――――――――――――――――――― 【著者】田中広美(ジャーナリスト) 【写真】NEXCO東日本公式サイト『もっと知りたい高速道路図鑑』より
(http://www.e-nexco.co.jp/csr/wakuwaku/)
■――――――――――――――――――――
2012年秋、当時の石原慎太郎都知事が急遽、国政復帰を表明。それに伴い12月に都知事選が実施された時も、内田の前に自民党都議団は「沈黙」を余儀なくされた。
なぜか。それは以下のような事情があったからだ。
石原が後継として使命した、作家で都副知事だった猪瀬直樹を、内田茂は極めて嫌っていると言われたからだ。そのきっかけは、千代田区紀尾井町の参議院議員宿舎の移転問題だった。
副知事に就任すると、猪瀬はメディアを引き連れ、宿舎の建て替え予定地を視察。結果、自然保護を理由に反対したのだ。
これが虎の尾を踏む。移転を推進していた内田茂の怒りに触れたのだ。以来、内田は猪瀬を徹底的に嫌厭する。ために自民党都議団も、猪瀬との不仲を伝えられるようになった。
その影響は、都知事選で露骨に現れる。自民都議団は猪瀬推薦を決定できず、最後の最後まで沈黙を守った。内田を慮ったと見られても仕方がなかった。対して選挙公示に先立って行われた自民党による世論調査では、猪瀬支持が40%超という結果が出た。猪瀬を容認できない自民都議団としては苦々しい展開に追い込まれていた。
最後は都議団での意思決定は不可能となり、公示日の直前、態度未決のまま判断を自民党本部に預ける形となった。そして最終的には党本部の決定で「猪瀬支援」が決まり、他党も有力候補の猪瀬に相乗りすることとなり、蓋を明けてみれば430万票超という歴史的数字で当選を果たす。
自民党都議の中にも、なぜこれほどまでに内田が猪瀬を嫌っているのか──参院宿舎の問題で猪瀬副知事が、内田都議の意向に反対したとはいえ──これほどまでに執拗に尾を引いているのか訝る向きもあった。
その背景として、内田当人でさえ自覚していない可能性もあるが、猪瀬が道路公団改革で「道路族のドン」と徹底的に戦ったことは重要だろう。猪瀬は勝者となり、相手を追放してしまったのだ。
猪瀬が引きずり下ろした相手は、元建設省事務次官で、元道路公団総裁の藤井治芳。そして藤井と内田茂の間は、やはり山田慶一が取り持っていた。
〝全知全能の神〟たる「道路族のドン」藤井治芳
山田たちが赤坂の焼肉屋『牛村』で宴会を開いた場面を、この連載では何度も紹介している。
第8回「角栄」
(http://www.yellow-journal.jp/series/yj-00000320/) 第15回「人間不信」
(http://www.yellow-journal.jp/series/yj-00000457/)
山田は、この会合の直後、藤井治芳の「直筆メッセージ」を自身のところに集う者たちに伝えた。それを道路のドンからのご託宣ととった者もいようし、はたまた、藤井からの直筆メッセージを得てくる山田という男の凄さを更に確信した者もいよう。
内容は、経済談義の他愛のないものだ。しかし藤井の直筆メッセージであることが「山田慶一」という看板がなお求心力を得るための何よりも強いメッセージとなる。
「藤井所感」とでも戯れに名付けてみるが、ポイントは以下のようなものだった。
経済再編に当たっての考え方 経済、特に金融・産業の国際化が一層重層化する中で、国際的なシステムへの参画がより弾力的に可能となるよう、努力すべき 例えば ○税制のあり方、その中でも関税のあり方 ○国際企業へ成長していくための育成プログラムの見直し
○外圧を利用した国内企業へのバッシング(パシフィックコンサルタント)
パシフィックコンサルタントがバッシングの一例として言及されているところが、いかにも山田らしい〝手配〟であるようにも見える。
自身が逮捕直前まで追い込まれた──実際、無罪とはなった──ものの、東京地検特捜部が立件した事件が、元建設省の事務次官をして「外圧を利用したバッシング」の一例としてわざわざ持ちだしている。
これこそが肝なのだ。山田の元へ参集する一流企業勤務の〝賢い紳士〟たちは、山田と藤井の「精神的な一体感」を見過ごすことなく、見事に嗅ぎ当てる。「山田劇場」で演じられる仕掛けは大胆かつ繊細。観客たちが〝見巧者〟ということもあり、芝居の意味を誰もが完璧に理解する。
藤井所感はレポート用紙3枚。地域金融と国際化など、マクロからミクロまで目配りがきいていた。しかし意外にも、「都市計画における研ぎ澄まされた思想性」などといった、プロを唸らせる魅力に乏しかった。藤井の圧倒的なキャリアを重ね合わせれば、凡庸という評価が下ってもおかしくない。
それは、日本社会を論じた次の一節からも伺えた。
日本社会は、明治政府発足以来、国家の体制が、諸外国に対して、国を富ます、強くする視点から、中央の強化と国家の強化を同一視し、税制、財政、法制、行政等を含め、インフラ構築も特別扱いされてきた。
国即ち中央と地方との関係は、廃藩置県、官制知事、地方への助成金システムといった視点でつくられてきた。
このことが、日本では、東京と地方との関係が必要以上に〝格差〟の形で現在に至っている。
全総計画で当初から〝一極集中是正〟が挙げられているのはその為である。
しかし、江戸時代では日本の文化、知識層が300雄藩からなる地方社会に定着しており、江戸に一極集中するのでなく、ほどほどの強い中央(江戸)とそれなりに強い地方との連けい構造であった。
日本社会が、住み易さ、文化、経済的強さを目ざして、新たな地域社会構築(地方分権)を考えるためには、最近の諸々の情報及び情報発信のあり方が極めて重要になる。
東京という大都市社会の国民である東京の発注情報をもって、日本の情報と誤解されないよう注意する必要がある。(東京人が日本人という誤解、東京人は日本人の一部にしか過ぎないという認識をあらためて思う必要がある)
藤井所感のキーワードに「全総計画」がある。この全国総合開発計画こそは、まさに戦後自民党の55年体制を裏支えした国土開発計画といえる。
目的は日本のグランドデザインを描くというものだ。当初は高度経済成長期にその事務局は旧通産省の外局である経済企画庁に置かれていた。それが橋本行革を経て、国土審議会を所管する旧建設省がその所掌を獲得した。
各年次の予算獲得が各論だとすれば、全総は、いわば総論にあたる。そして、仮に各論が総論を超え得ないものだと考えれば、全総は「日本国デザイン」の設計思想ともいえる。更に踏み込んで表現すれば、日本国開発計画の「チャーター」──憲章、綱領、宣言などと訳される──とでもいうべきものだ。
旧建設省の事務次官・藤井治芳が道路族のドンとして君臨できた背景の1つは、国土交通省が土建行政の元締だからというだけではなく、日本国土の設計思想さえもデザインする組織であったからだ。
山田は、その「全総」を築いてきた藤井のメモを、つまりは「ドンの心情」を〝代読〟できる存在なのだ。山田こそは「日本開発のドン」の〝使用人〟であるという空気を醸し出していく。
〝道路利権〟を巡る通産省と建設省の暗闘
現在、旧建設省=国土交通省が所管する全総は、そもそも旧通産省=経済産業省が担当していたことは、専門家の間でも、あまり知られていないようだ。
先述した通り、全総は日本のグランドデザインを描く総論にあたる。当初は経済企画庁が所管し、経企庁は内閣府の外局として設置された。しかし、設置時にプロパー職員の存在しない官庁は、既存組織によって所掌争いの草刈場と化す。
経企庁を巡るヘゲモニー闘争に、当然ながら旧建設省も〝参戦〟している。建設省は霞が関の中でも「隠れた名門」という個性を持っていた。藤井治芳のように、技官でも事務次官に上り詰めることができる技術官庁として知られるが、その出自は戦前の旧内務省に遡る。
戦後GHQにより、内務省は自治省、厚生省、警察庁などに分割されたが、こうした旧内務省系の省庁は現在でも〝選民意識〟が高い。省庁の垣根を横断し、「旧内務省関係者」の名簿を作成するなど、自らを「ノーブル」な存在だと任じている。
日本の省庁はエリート組織と見なされるが、1府13省庁の中で更に上位と位置付けられる役所を「五大省庁」と呼ぶ。内訳は①財務省、②外務省、③経済産業省、④警察庁、⑤総務省自治分野──となるが、この中で経産省=旧通産省は戦前、商工省と呼ばれ、決して一流官庁ではなかった。通産省が一流官庁として台頭してきたのは復興と経済立国が成功した戦後からになる。
そして1950年に誕生した経済企画庁は当初、通産省に〝占拠〟される。歴代の事務次官を見れば、当初は商工・通算官僚の名ばかりが連なる。経企庁プロパーのトップ人事が行われたのは何と1989年。星野進保・事務次官の登場まで待たなければならず、実に設立から30年が経過していた。
だが、名門建設省が、通産省の勝ちっぱなしを許すはずもない。最重要の仕事であるかのように暗闘が続き、遂に2001年の橋本行革による省庁再編で、全総の所管は通産省の手から建設省の手に移る。
この全総が描く、全国道路ネットワークの下積み作業に関わり、役人人生を全うしたのが藤井治芳である。1936年生まれ。東京大学工学部土木工学科、同大学院工学研究科を経て62年に建設省入省。
通産省=経産省は例えば、都市整備機構を所掌し、絶対に離さない。だが、道路で結ばれていない「単独の街」などあり得ない。都市を発展させるためには、必ず道路が必要だ。だからこそ藤井は戦後日本で行われた開発の全てを担ったと言っていい。生き字引だからこそのドンだったのだ。
そして山田慶一は自民党田中派・田中政権が生んだロビイストだ。田中派が持つ権力、その源泉の1つが道路だったことは言うまでもない。山田も、この藤井の影をちらつかせることで、企業の求心力と、自身の命脈をつないでいた。
ここで、少し重要な寄り道をさせて頂きたい。少なくとも、わが国日本において、民間が仕事をしようとすれば、必ず役所の「ルール」にぶつかるわけだが、そもそも、なぜ省庁の所掌が拡大し続けるのだろうか。更に、そうした指向の源泉はどこにあるのだろうか。この問いに、さる経産省の人間は、次のように答えてくれた。
「すべては法律。役所の権限はすべて法律が根拠になっているんだから。法律、政令、省令とね。役所は法律がなければ何もできないでしょ。だから、法律を作らなければどうにもならないわけだ。施策にはすべて法律が絡んでくる」
なるほど。省庁は法律を作れども、棄てないのには訳があったのだ。
「年間、おおよそで100本くらいの法律が成立しますが、廃止というのはほとんどないですね。廃止の場合でも、法律の一部を廃止することはあっても、法律そのものの廃止というのはまずない。改正、改正でやっていきますからね」(内閣法制局)
そして、経産省の人間はこう付け加える。
「法律を廃止するときはね、それは何を意味するかわかるかい? それは、新しい法律を作るときだよ」
法律を永遠に作り続けるのだから、所掌が拡大することはあっても、縮小することはない。そこに、商機ならぬ〝省機〟拡大の芽もあろう。
更に、省機拡大のときこそ、民間の思惑も潜り込む〝好機〟到来なのだ。1990年の橋本行革。その中の省庁再編とはまさに、バブル崩壊後の「失われた20年」の始まりであり、変革期特有の微妙な歪みが、ロビイストに付け込む余地を生んだのかもしれない。
更に言えば、田中角栄と、越山会の女王、佐藤昭を後ろ盾にする自民党の生んだロビイスト、山田慶一の生き残る余地を……。
山田慶一と対峙した東洋経済新報社記者の岡田広行
藤井治芳と全総計画。それは字義通り、開発そのものを意味した。
開発計画に関する情報を、いち早く入手することは、企業にとってはどこよりも早く「ツバを付ける」すなわち、カネを注ぎこめることを意味した。
使途秘匿金のニーズと、それが生きる余地がそこに生じるのだ。ちなみに使途秘匿金については、この連載の第13回で焦点を当てた。
【会員無料】『哀しき総会屋・小池隆一』第13回「千代田&練馬区長」の〝過去〟
(http://www.yellow-journal.jp/series/yj-00000444/)
ゼネコン業界にとっては、いわゆる「前捌き金」といわれる、優に億単位にのぼるカネが動くことになる。事業関係者を飲食で接待するカネに使われるのみならず、現ナマを〝握らせる〟ためのシステムといえた。
あそこにビルが立つ、向こうの駅前が整理される、といった計画が発表された段階で動いても、もう企業の事業は成り立たない。計画段階からカネを注ぎ、計画そのものを時には動かし、原案に食い込み、素案に意志を反映させる。そんな時にこそ「前捌き金」は大きな力を発揮する。
藤井治芳という〝神〟の思想が、山田という〝口〟を通じ、ゼネコン業界と、その周辺に現実的なメッセージを伝える。すると、そこに集い、行動を開始する者たちが現れる。
しかし、それが現在進行形として立ち現れる時、あまりに生々しく、醜悪な姿態を曝すことにもなる。東京都千代田区紀尾井町・清水谷参議院議員宿舎の老朽化にともなう移転・建て替え計画もまた、実はそんな壮大な思惑の一端にしか過ぎないのかもしれない。
それにしても、この山田慶一という一般には耳慣れない無名の人物になぜ、これほど多くの人間が〝惹かれ〟、そして〝恃み〟とするのか。山田の素姓についてはほとんど活字になったことはないが、その山田を長く〝監視〟し続けてきた記者がいる。
東洋経済新報社の岡田広行だ。その岡田が書いた次の記事が、これまでにもっとも深く、その山田を追ったものといえる。
岡田がかつて取材した段階では読み解けなかった部分に、その後、私の取材で新たに読み解ける部分を加えて補完しながら、引用してみたい。
山田慶一氏。
「業務屋」と呼ばれる建設談合の世界に身を置く人間であれば、一度ならず彼の名前を耳にしたことがあるはずだ。
昨年2月、公正取引委員会に一通の〝告発文〟が持ち込まれた。
表題は「独占禁止法四五条一項に基づく申告」。差出人は平島栄・西松建設相談役(当時)。近畿二府四県の建設談合を取り仕切ってきた実力者が、部下の談合屋の造反に激怒して、前代未聞の行為に及んだのだ
〝談合のドン〟、平島のこの暴挙ともとれる行為は、当時、ゼネコン業界にとどまらず、それを持ちこまれた役所側にも衝撃を与えた。このスキームを描いたのが山田である。
その平島氏が「すべてを明るみに出す」と息巻いていたさなか、談合の実態に詳しい準大手ゼネコンの幹部がポツリと漏らした。
「平島さんの背後で、『山田慶一』が動いている。話がややこしくなってきた」
山田氏は、経歴、生年月日、出身地とも不詳。
過去の事業歴を調べるには、法務局に眠る膨大な閉鎖謄本を丹念にめくる以外にない。しかも、一三年前に遡らなければならない。当時、山田氏は、「ケイヨウエンジニアリング」(本社・港区)なる企業の代表取締役を務めており、同社が二度目の不渡りを出す四カ月前に代表の座を退いている。以来、なぜか世間の表舞台に出ることを避け続けてきた
山田の経歴はたしかに、表向き不詳である。当人が語らないのみならず、当人に訊くことさえ憚られる、強い威圧感を放っているからである。
あるいは、誰もが知る「在日」という素姓ゆえに、山田を知る人間に自発的な抑制を強いているのかもしれない。
だが、警視庁のファイルによれば、山田の経歴については次のように記録されている。
山田慶一はもちろん、日本でのいわゆる日本人的な〝通名〟であるが、この通名もかつては慶一ではなく、初男で通っていたとされる。
山田初男は、山口県出身とされる。それも、九州にもっとも近く、関門海峡をのぞむ下関市という。
山田の学歴もこれまた表向きには、日本大学中退とも、東京理科大中退とも、他称されているが、これは、山田がこれら2つの巨大な学校法人を巻きこんだ巨大な都市計画プロジェクトに参画する折々にどこからともなく囁かれた話であり、事業の展開に有利に働くとみるや、それぞれの局面で都合のいいほうにあえて〝流している〟気配が強い。
警察当局は、山田の最終学歴を「日本不動産専門学校」と見ている。同名の専門学校は現在も福岡市内に存在するが、山田が幼少期から青年期にかけて下関で過ごしたとすれば、福岡の専門学校に通っていたとしても不思議はない。
下関と福岡とは、関門海峡という海を挟んではいるが、〝通勤圏〟である。
この後、山田が警察当局に補足されるのは、「林一家」の構成員としてである。林一家とは聞き慣れないが、それも無理はない。かつて横須賀界隈を拠点として展開した林喜一郎率いる任侠グループで、林は稲川会最高顧問であった。この林一家の若い衆として、山田は初めて警察当局に補足されるのだ。
この林一家の領袖、林喜一郎が死去した1985年以降、「山田初男」は表から姿を消した。
そして、いつしか立ち現れたのが「山田慶一」である。山田の朝鮮名は朴慶鎬。おそらく、新しい通名に、「慶」の一文字を入れたのであろう。在日の人間が日本語の通名を創る場合に、当然、本名とのつながりをどこかに残す作法にもかなっている。
この山田初男が構成員として認知されていた林喜一郎一家だが、林一家は、いわゆる〝経済ヤクザ〟のパイオニアといわれ、単なる任侠道から、現在につながる事業性へシフトする先鞭をつけたことでも知られている。
山田初男が日本不動産専門学校で身につけた不動産取引の知識が、そうした事業性を追求する林一家で重宝された場面もあったのかもしれない。
さらに、岡田が突き止めた「ケイヨウエンジニアリング」における山田の役員歴は貴重といえた。山田は現在まで種々に顧問の名刺を持つものの、ある時期以降、法人の役員登記欄には一切、名前を出さないからである。
山田が〝自分の会社〟といいながら、「経営者」として正式に名前を表すのは、これまでに知られているところでは、このケイヨウエンジニアリングと、そしてもうひとつ、かつて赤坂にあった料亭・鶴仲くらいである。その他は、オーナー然とした振舞いをしながらも、決して役員欄には登場しない。
「山田は不動産には長けているが、株などの数字はまったくわからない」(小池隆一)といわれるそのあたりの偏りも、あるいはそのキャリアに由来しているのではないかとさえ思わせる。
実際、自身にまつわる不動産の抵当のつけかたと、その転がし方、つまり不動産を、売買を経ずしてカネにする作法には山田は実に長けていて、自信を見せる。
そして、その人脈は確かで、彩り鮮やかである。
反面、政官財の人脈は多彩だ。
「越山会の女王」の異名を持つ佐藤昭子女史(政経調査会)、佐藤茂・川崎定徳前社長(故人)、加藤六月・衆議院議員、藤井富雄・公明元代表(東京都議)の長男・練和氏、そして葉山莞児・大成建設副社長等々。
主催するパーティーもスケールがでかい。毎年暮れになるとホテルの大広間を借り切り、ゼネコン幹部数百人を招待して忘年会を催すという。出席者は互いに顔を見合わせ、「どんな人がよく知らないが、すごい人脈を持つ人らしい」と囁きあう。パーティーの費用の捻出方法も不明である
だがバブルが崩壊し、自民党による圧倒的な利権政治と土建体質も多少の変革も迫られてきた昨今は、山田自身の経済状況も下降の一途を辿っているようだ。
「かつてのような神通力はもう失われつつある」(山田と20年来の知人)との声もあり、近年は赤坂の元クラブの焼肉屋の奥座敷で粛々と行われているにすぎない。
しかし、そのスケールは異なれども、互いを知らぬ多彩な人脈こそが自身に対する求心力につながることを知悉し、そのための演出を躊躇なく駆使するあたりは、過去から現在に至るまで一貫している。
本誌は山田氏の事業を二年以上にわたって追い続けてきた。山田氏が関与したプロジェクトの多くが不良債権と化しており、少なからぬ事業で「疑惑「の存在が囁かれてきたからだ。
今年度末にかけて、銀行の不良債権処理に六兆円の公的資金が投入される。不良債権を作った責任は厳しく問われねばならない。だからこそ、山田氏には事業が頓挫したいきさつを聞きたかった。
すると、思いがけないことに希望がかなった。文化学園の不祥事を取材するさなか、本人から「会ってもいい」と連絡が入ったのだ。この間、電話での取材依頼は優に一〇回を超えていた。山田氏が手掛けた東京・日の出町の山林開発の取材を始めた時から、すでに二年の歳月が経過していた。
11月半ば、本誌記者は山田氏が主宰する団体の事務所におもむいた。千代田区一番町。日本交通の子会社が所有する真新しいビルの八階に山田氏は本拠を構えていた。中では七、八人の中高年の男女が働いているが、仕事の内容ははた目には分からない。
「環境計画研究会 山田慶一」
差し出された名刺は、シンプルなものだった。ちなみに「環境計画研究会」は法人登記がされていない私的な集まりである。ただ、三年前に東京都に提出された宅地建物取引業者の資料の中に、次のような記載があった。
「本来、林野庁の遊休化した土地の再開発をするために(株)リスト内に設置された勉強会であり、目的を達成した現在も、ゼネコンその他不動産間連業者を集めて勉強会を開催しています」
ちなみに、「リスト」の関山靖人社長は、右翼団体の「輿論社」に勤務していた経歴を持つ実業家で、山田氏の最も緊密なパートナーの一人とされる。リストと環境計画研究会は、同じビルの一室に事務所を構えていたこともある
山田はしかし、この関山とのトラブルを抱える。これが、記事中でも言及されている東京西部の日の出町の開発を目論んだ、西東京開発をめぐる案件で、このときの反動も大きく影響したのか、ゼネコン大手の青木建設の倒産にも一役買った。西東京開発については岡田が記事中で後述する。
山田氏の名前は、意外なところでも登場した。大沼淳・文化学園理事長の娘婿だったのだ。だからこそ、山田氏は本誌記者の動向に神経をとがらせていたのだ
山田が子どもをもうけた〝妻〟はこれまでに都合6人に上ると見られている。
この数は2007年、山田の実母が亡くなった葬儀の席で、初めて参列者らの目に触れ、明らかになった。
文化学園理事長の娘は、このうちの1人で、山田はやはり子を1人設けている。だが、戸籍上の理由からか、山田は「これまで一度も結婚歴はない」と親しい者に喧伝している。つまるところ、籍を入れたことはないというのが実態のようだが、大沼の娘婿であった一時期、山田をマークするもうひとつの眼があった。
当時の写真週刊誌『FOCUS』(新潮社・休刊)編集部である。所属記者やカメラマンは山田を追い、数々の写真を収めている。編集部が山田をマークしたのは、やはり平島栄による談合告発事件が契機だった。地下に潜っていた「初男」が「慶一」としてメディアに注視されるようになったのは、やはり平島栄事件が転機とみていいだろう。
西松建設の平島栄、そして文化学園理事長の大沼と、常に大きな図体の後ろに身を隠すかのような生き方をしながら、徐々にその防御装置が完全には機能しなくなる。
それは、関わる事業の大きさというよりはむしろ、自民党による圧倒的で絶対的な支配構造がほころびを見せ始める、時代構造と社会情勢の変化に曝されていたと読むほうが自然なのかもしれない。
だが、自民党を背景に、山田らは「日本」を掘り起こし続けようとした。そこに、実はもっとも大きな落とし穴が待っていた。そして、その穴の底には亀裂が見えていた……。
週刊東洋経済の岡田はついにその山田と対面する。
山田氏に聞きたいことは山ほどあった。まず第一に「平島事件」の真相。次に、三〇〇億円が注ぎ込まれた東京・日の出町の山林開発事業の挫折の軌跡。そして、汐留地区での再開発事業の行方。そして文化学園の一件である。
「私の周りをあれこれお調べのようですね。私に何を聞きたいんですか」
山田氏は、一瞬当惑した表情を浮かべながら切り出した。そしてすぐさま苦言を呈した。
「あなた方は以前、私が関係する『西東京開発』に七〇億円の使途不明金があると書きましたね。そんなカネは一銭もありません。きちんと調べてください」「西東京開発」とは、東京・日の出町の山林開発を目的に設立されたプロジェクト会社である。青木建設、熊谷組、ハザマ、五洋建設などゼネコン六社が三〇〇億円近い債務を連帯保証したものの、事業は行き詰まった(本誌『96年10月5日号』参照)。
「そんなはずないでしょう。こちらも関係者を取材しています」
記者が食い下がると、山田氏は興味深い発言をした。
「使途不明金はないのです。(住宅・都市整備公団出身の)元社長が目的外の事業に使ったカネが約三〇億円ありましたがね。原宿で土地建物を買ったんです」
記者は思わず息を呑んだ。
「ですが、すでに時効です」
山田氏はこう締めくくった
山田の口からいみじくも洩れた「時効」という言葉。山田がしばしば表舞台から姿を消す時、民法上の時効がつきまとう。
それが果して「時効成立」を待つための意図した行為なのかどうかはわからないが、山田が看板を下ろして、あるいは息を潜めている間に、しばしば多くの「時効」が成立し、関係者らは路頭に迷う。
小池隆一もまた、山田の時効主張を目撃したことがある。関係者が歯ぎしりしたときにはすでに時効は成立し、そして刑法上の訴追を受けることもまずない。そうした関係者らの心理には、山田との〝共益関係を築かされてしまったのではないか〟という一抹にして大きな不安が必ず植え付けられているからである。
「山田の手口には、そうした共犯心理を共有させるところにひとつの特徴がある」(小池)のだ。それを、しかし、商売上手と呼ぶには、いささか無邪気が過ぎるだろう。山田以外の周辺関係者はそれによって、事業、そして企業、そして詰まるところは個人の生活が破綻するなどして、決定的な犠牲を生むからだ。
山田がしかし、偶然ではなく、「時効」という概念をしっかり認識していることの言質をとった岡田との対峙は続く。
(第17回につづく)