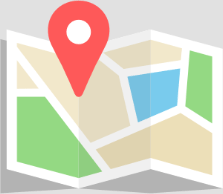2017年4月6日
【無料記事】記者会見でPC叩く「ぱちぱち記者」の愚

東京・大阪証券取引所が経営統合を行い、2013年に発足した日本取引所グループ(JPX=東京都中央区日本橋兜町)は毎月、清田瞭・グループCEOの記者会見を開く。出席者は東京株式市場を担当する記者クラブの記者たちだ。
例えば2月の定例会見は27日に行われた。清田CEOが当月の取締役会の決定事項を伝え、そのあと各記者による質疑応答。話題の中心は当然、東芝問題だったという。だが、Q&Aの内容よりも、JPXの関係者には気になることがあった。
それは記者会見の間、ひたすらパソコンを「ぱちぱち」打つ記者たちの存在だ。「ぱちぱち君」と呼ばれることもある。
会見に出席しながら質問もせず、話し手の顔や動作も見ず、ただパソコンの画面を睨みながらキーボードを打つ。文字通りのマシーンだ。とはいえ、「ぱちぱち君」の姿は意外に多い。10人近くいるときもある。
質疑応答が白熱しても、「ぱちぱち」という音は聞こえ耳触りこのうえないが、彼らの手は止まらない。その異様な光景を「どうにかしたい」とJPX関係者は考えた。そして、ある日、朝日、読売、日経、共同のキャップたちに聞いて回ったのだという。
■―――――――――――――――――――― 【写真】ぱちぱち君が叩くPCのキーボード
■――――――――――――――――――――
「ぱちぱち君、どうにかなりませんか?」
各社とも「何とかしたいですねぇ」と苦笑。だが、しばらくすると、そのうちの1人が「でも……」と呟いた。
「私は、あんなのいらないと思っています。でも本社のデスクが記者会見の会見録を欲しがるんですよ。それもすぐに」
別の社のキャップも同意する。
「我が社なんか編集委員も会見録を欲しがりますよ。『早くメールで送れ』と催促してくるぐらいです」
結局、4社のキャップは全員、同じ意見だった。「だから私たちの一存で止めさせることができないのです」──JPX側は、ため息をつくばかりだったという。
それにしても、会見にパソコンを持ち込み、質問を一切行わず、ひらすら質疑応答を入力する記者が出現したのは、いつの頃だっただろうか。
さる記者も疑問に感じ、周囲に訊いてみたという。「東日本大震災の頃から目立ってきたかなあ」との回答が多かったという。
震災以前はICレコーダーを会見者の前に置き、記者は椅子に座って会見の内容をノートにメモ。そして時には会見者の身振り手振りを見て質問を発していた。レコーダーに録音した内容は、会見が終了するとメモにおこし、自らが保存した。
ところが東日本大震災が発生すると、政治部デスクが記者会見の会見録を欲しがるようになった。更にメール回覧が普及。勢いづいて社会部、経済部と広がり、今ではほぼ全ての会見で「ぱちぱち君」が出没するようになった。
メディアの最重要事項は、事件や事故といった「突発的ニュース」を報道することにある。当り前のことだ。だからこそ現場には、全世界のどこにであっても、必ず記者が派遣される。
現場記者は事件や事故を最も知る記者だ。情報が集約する「本社デスク」が逆立ちしても敵わない。某人気刑事ドラマの映画版では「事件は会議室で起きているんじゃない! 現場で起きているんだ!」の台詞が話題になったが、全く同じなのだ。
現場記者が取材し、デスクに報告・相談して記事化していく。デスクは現場記者に全幅の信頼を置く。それが普通だろう。
だが、現場の会見録がメールで早急に送られるようになり、記者とデスクの関係に変化が生じてきた、という意見の記者は少なくない。デスクが「まるで現場にいるかのように」指示を出してくるようになったのだ。
細かい話をすれば、特に新聞社は「新人の現場記者」→「現場をまとめる中堅のキャップ」→「本社や支局にいるデスク」という報告経路を通じ、記事化が行われていく。
ところが「ぱちぱち君」のメールを見たデスクは、キャップの頭越しに現場記者へ指示を出すようにもなっていく。一見すると合理的に見えるが、「キャップが成長する機会」を奪っているという問題がある。
更に「ぱちぱち君のメール」を心待ちにする上層部もいる。編集委員や解説委員だ。なぜなら、日ごろ付き合っている政治家や経営者にまるでそこにいるように話ができるからだ。「東芝ではこうだった」、「首相はこういった」……などなど。
あるキャップは、皮肉たっぷりに付け加える。
「ぱちぱち君の彼らも喜んでいるんですよ。『デスクに喜ばれる』とね」
会見者の真意を読み取り、読者に代わって質問し、回答を聞き切り返す。そんな記者の基本動作である取材を行わず、速記マシーンに徹することに喜びを感じる記者が少なくないのだ。大抵の「ぱちぱち君」は「支局上がりの3~4年目が多い」という。それは今から本社で油が乗る年代のはずなのに、「上司に気に入られることが喜び」とは、サラリーマン・ジャーナリズムが基本の日本らしい話である。
記者に限らず、新人を育てるのは畑で作物を育てるのと同じだ。必要なときに水や肥料を与え、ときには添え木する。誰がやっても大変の一言に尽きる。しかし今、各社のデスクは現場の会見録を見る喜びを優先させ、記者を育てることを止めた。かくて「ぱちぱち君」は今日も会見場を跋扈し、メディアは「マスゴミ」と馬鹿にされ、どんどん読者が離れていく。
(無料記事・了)
2017年4月5日
【無料記事】「全柔連会長」定岡正二氏の「爆弾コラム」は「講道館廃止」

2016年12月、日本経済新聞・夕刊の1面コラムに、新日鉄住金と、全日本柔道連盟の会長を務める宗岡正二氏が「日本柔道の課題」と題する提言を書いた。掲載から数か月が経過しているが、「あの中身は爆弾級だ」と、じわじわ波紋を広げているという。
宗岡氏は、ロンドン五輪の翌年に噴出した暴力問題や不正経理などの不祥事を受け、日本柔道界の再建のために全柔連会長に就任。以来、組織改革を急ぎ、リオ五輪でも一定の成果をおさめた。
このことに宗岡氏は自信を深めたのだろう。件のコラムで柔道界の「最後の課題」として掲げたのが、全柔連と講道館の関係だった。
■―――――――――――――――――――― 【写真】講道館公式サイトより
(http://kodokanjudoinstitute.org/)
■――――――――――――――――――――
<最後の課題は、日本の柔道界に併存する、柔道競技全般を担う全柔連と段位認定権を持つ講道館という二つの公益財団法人のあり方の追求であろう。剣道では全日本剣道連盟が段位認定も担う等、日本の他の競技ではこのような形での二つの組織は併存しないし、諸外国の柔道団体もしかりである。組織運営上さまざまな問題が生じるからであろう>
講道館の持つ「段位認定権」に疑問を投げかけた上で、更に「日本の柔道界に詳しい外国の友人」に、こう語らせた。
<「日本の柔道界に業務が重複するような二つの団体が存在するのは問題ではないか。講道館を柔道のレガシー(遺産)として全柔連の付属機関とし、早稲田大学大隈記念講堂のように『全柔連嘉納記念講道館』とすれば多くの問題が解消されるのではないか」>
新聞記事だけあって、文体は品のいい優等生スタイルだ。なおかつ外国人に語らせたため、婉曲の効果も生まれている。
とはいえ、確かに内容は強烈だ。要するに講道館が「家元」として〝既得権益〟を独占していることを批判し、解体を提案しているのだ。
講道館が発行する段位については、1981年にも国際柔道連盟(IJF)が独自の段位を発行するとして、講道館と全面対決したことがある。同時に、全日本学生柔道連盟も正力杯主催の読売新聞を後ろ盾に講道館と衝突、全柔連からの脱退を表明した。
当時、IJF会長とともに学柔連会長を務めていたのは、東海大総長の松前重義氏(故人)であった。さまざまな仲介を経て、対立は「講道館=全柔連」側の勝利に終わったものの、無傷というわけにはいかなかった。IJF内において、特に全柔連の立場は弱体化の一途をたどっている。
宗岡氏のコラムは、そうした対立の再燃を予感させるものだ。しかも、その根が深い。
宗岡氏は東京大学柔道部の出身。講道館柔道とはルールも違う「高専=七帝柔道」で鍛えられた。寝技、絞め技を中心とする高専柔道は、精神的にも講道館と一線を画しているのだ。
松前氏も、読売の正力松太郎氏も高専柔道の出身である。現在の全柔連専務理事の元警察官僚、近石康宏氏(67)も東大柔道部で宗岡氏の後輩だ。一方、副会長の山下泰裕氏(59)は松前氏の東海大組である。
極論を承知で言えば、気がつけば全柔連幹部は「講道館色」を失いつつあり、「高専柔道色」が濃くなっているのだ。当然ながら講道館側の危機感は強い。
図式としては、講道館にとって段位認定権こそが、最後の牙城であることは間違いない。もし宗岡コラムの提案が実現し、認定権を失ってしまえば、講道館は経済的にも無力化していくことは間違いない。
(無料記事・了)
2017年3月8日
【無料記事】読売VS朝日「年始スピーチ」の勝敗

大手新聞社トップが年頭に何を語るか。その年を占う上で例年、大手紙トップの挨拶は注目されるが、中でも『読売新聞グループ』のドンとして君臨し続ける『ナベツネ』こと渡邉恒雄・代表取締役主筆は、90歳とは思えぬ怪気炎を今年も賀詞交歓会でぶち上げた。
ナベツネ氏の話の中で話題を呼んだのは、ライバル紙である『朝日新聞』の元日から始まった年始連載を取り上げ、猛烈に批判したことだった。
その発言内容を抜粋してみよう。
■―――――――――――――――――――― 【写真】朝日新聞公式サイト『会社案内』より
(http://www.asahi.com/corporate/?iref=comtop_footer)
■――――――――――――――――――――
「朝日の新連載が始まりまして、タイトルは『われわれはどこから来て、どこへ向かうのか』、副題は『成長信仰』、見出しは『経済成長、永遠なのか』……。簡単に言うと、低成長を容認しろ、ということです」
などと、朝日新聞が打ち出した「成長否定論」を指弾したうえで、朝日の別の日の国際面の特集に話を転じた。
その日の特集では、経済の低成長が格差拡大を招き、政治への不信が高まり、欧州危機を招いた――という「成長肯定論」であり、先の新連載とは真逆の論調になっていた。ナベツネ氏はこれを指摘し、「どうも全体が一貫していないなあという気がします」と一刀両断にした。
さらにナベツネ氏は、国際情勢、社会構造からデータを駆使して独自の鋭い分析を開陳し、「僕が朝日新聞の低成長容認論に反論するのは、成長をあきらめていたら日本は第4次産業革命に乗り遅れていく。『成長いらん』と言ったら、どうなるのか」と激しい口調で朝日を批判したのだ。
それでは、ナベツネ氏に〝あてこすられた〟朝日新聞の渡辺雅隆社長(57)は、年頭に何を語ったのか。
渡辺社長は、新聞事業以外の新規事業計画を詳細に述べ、有力投資ファンドから『社長室戦略チーム』に社長補佐として2人の人材を迎え入れたことを明らかにした。
そして資産活用や企業買収の可能性に言及。「成長事業の創出は最優先課題です。目標の達成に徹底的にこだわっていきたいと思います」と、高らかに「成長促進」を宣言していた。
自らの企業の成長にはあくなき「追求」を主張し、新聞購読者には「低成長もやむなし」と主張する姿には、ナベツネ氏ならずとも、業界筋からは「さすがに朝日新聞の伝統〝ダブルスタンダード〟は今年も健在ですね」と揶揄されている。
一方、経済界からは朝日新聞に対し、こんな声が出ているのだ。
「低成長を容認する紙面をつくるのなら、広告出稿やイベントの協賛などのしつこい営業もやめてもらいたいものです」
(無料記事・了)
2017年3月7日
【無料記事】「安倍政権ブレーンの横顔」苦労人「谷内正太郎」

少なくとも見える成果は皆無となった、2016年末の日ロ首脳会談。だが会議が終了した直後、安倍晋三に食い込み、今やべったりの関係を構築したNHKによる特集番組に、私の目は釘付けになった。
■―――――――――――――――――――― 【筆者】下赤坂三郎 【写真】内閣官房公式サイト「幹部紹介」より
(http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/kanbu/2013/yachi_shoutarou.html)
■――――――――――――――――――――
もとより成果のなかった会談だ。いくら裏話を掘り出しても、それほど面白いわけではない。独占密着を果たしたNHKが気の毒に思えるほどだったが、首相本人が登場するインタビューに、ある人物が画面に映った瞬間、全てが納得できた。
安倍が私邸の敷居をまたがせる「もう1人のアッキー」こと、岩田明子・NHK解説委員らしいロングの黒髪が映りこんでいたのだ。
やはり安倍は、2人のアッキーに護られているのだと──〝本家〟アッキーは最近、「アッキード事件」で夫の足を引っ張ってはいるが──つくづく納得させられた画面ではあった。
それはともかく、前後して登場したプーチンを待つ間、安倍を囲む側近だけの極秘会議の場面は、文字通り刮目に値した。
テーブルに就いていたのは、元外務事務次官の谷内正太郎だったのだ。
私は1月4日、山内昌之氏を取り上げた。
『【無料記事】「安倍政権ブレーンの横顔」ルサンチマンの「山内昌之」』
(http://www.yellow-journal.jp/series/yj-00000419/)
谷内は山内昌之とも近しい、内閣安全保障局長である。もとより、山内を安全保障局の顧問に招いた当人の1人が谷内であるのだから当然であろう。
だが、当の外務省プロパーからすれば、この谷内という存在はいささか特異なものに映るようだ。
安倍外交のまさにブレーン中のブレーンとなった谷内だが、外務省OBや現場からの視線には冷ややかなものも少なくない。なぜか──。
谷内は、大使を経ることなく次官に上り詰めた異質の外務官僚だからである。
谷内が安倍とべったりとなったそもそものきっかけは、小泉政権において安倍が官房長官に抜擢された時期に遡る。その意味で、現在、側近中の側近といわれる経産省出身の今井尚哉は安倍の第1次政権以降の人材であるのに対して、その付き合いは古い。
安倍のタカ派外交で理論的側面を支えてきたのが、この谷内だ。大使を経ていないからといって、それが外交官としての手腕、外交政策の視点に決定的な影響を及ぼすとは言い切れない。
しかし、外交現場の矢面に立つのが各国における大使だとすれば、それを経験していない谷内は、いかにも理論先行で、パワーポリティックスを肌で身をもって知らないということにはなる。
「外交は実は理論ではなく、経験が決定的でもあり、とりわけ痛い経験の蓄積こそが大事」とも言われるぐらいだ。
一気に上り詰めてきた安倍の思想信条に共鳴するまま、やはり次官に上り詰め、最終的に外務省の外の外務省という中途半端な安全保障局長に収まった谷内に対して、外務省内から冷ややかな視線が浴びせられるのは、こんな背景がある。さる外交官が打ち明ける。
「安倍にしてみれば、安全保障局に元外務次官の谷内を迎えることで、外務省も抱き込んだつもりかもしれないが、外務省は伝統的に、全省あげて、ということはない。欧州亜のそれぞれのスクールに分かれて、それこそ戦前の海軍陸軍並みの強烈な競争と派閥争いを繰り広げている。どこの大使も経ていない谷内が外交の現場をわかっているなどという者は外務省にはいない」
その谷内は富山県出身で石川県金沢育ちと伝えられているが、血筋のいい外務省のなかでは、珍しい叩きあげの部類である。
そもそも、富山から能登にかけて点在する「谷内=やち」姓の源流は、富山・南砺地方の山中奥地を源流とする一帯がひとつの発祥とするとみられている。
最源流は世界遺産ともなっている、おわら風の盆でも知られる五箇山界隈であり、かつて加賀藩時代は、いわゆる政治犯、思想犯の流刑地であった。谷内姓はここを源流に、山をくだり、能登の先まで向かう途中で「牛谷内=うちやち」などと時と場所と職業に応じて姓のバラエティーを変化させていった。
とりわけ富山から金沢にかけてくだった谷内姓の多くは、戦後のダム事業によって水没集落となった者たちによる集団移転や就職事情を背景とするものが多い。彼らのうち、優秀な者は石川県の金大附属や富山高校を経て上京し、外務省へと入省するが、ここで北陸閥は外務省内においても一大勢力を築いてきた。
谷内という一族がまとった歴史的な水脈を辿れば、立身出世意識の極めて強い裏日本・北陸のさらに傍流としての苦難の道が見えてくる。
たたき上げのなかのたたき上げ、そんな風景も見えてこよう。ならばこそ、一度つかんだ椅子は決して手放さず、権力への渇望と飽くなき執着は納得もできる。
血筋のいい外務官僚らが大使の椅子に座るも、決して泥臭い次官レースに躍起にならないのに対して、安倍という上昇権力を握った谷内が、決してそれを手放さなかったのは、安倍の側の事情をおいても、理解はできる。
安倍外交の枢要でありながら、そんな谷内の「外交観」はほとんど不明であるのも政権の最大の謎のひとつである。
次官時代の谷内は、外交よりもむしろ、国内の情報操作に長けていた一面がある。外務省の記者クラブ「霞クラブ」に所属していた放送関係の記者が明かす。
「次官時代の谷内さんは新聞だけでなく、雑誌の編集長クラスともこまめに会食していましたよ。だから安倍さんが彼を重用したのは、外交上の情報収集力や分析力というよりも、国内向けの目配せのうまさであったのかもしれないなと思いましたね。局面に応じたひとたらしのうまさでいけば、それこそ電通や博報堂の人間並みにうまいです。ただ、あくまでもそれは国内向け、日本人向けですからね。外交の現場で通用するかどうかは、当の外務省の部下たちにも正直、わからなかったというところでしょう。なにしろ、谷内外交そのものには、実績がなかったというの現実ですから。どちらかといえば、旧内務官僚型であり、外交官というにおいはあまり強く感じなかったぐらいです」
安倍外交のプレーヤーは、もちろん安倍晋三本人だ。父・安倍晋太郎は中曽根政権で外相を4期務めている。その姿を意識している側面があるはずだが、なぜか多くのメディアは安倍外交のシナリオを描く谷内に焦点を合わせようとしない。まるでブラックボックスだと諦めているようなのだ。
メディアの〝弱腰〟を見ると、放送記者氏の述懐が更に重く響いてくる。次官時代に繰り広げた、旧内務官僚ばりの「記者たらし=マスコミ統治」が好を奏しているのかもしれない。
(無料記事・了)
2017年3月1日
【無料記事】日経「ネット記事後追い」騒動と「AI記者誕生」

東京・兜町。ここに日本株式市場の中心たる、東京証券取引所が建っている。
取引所の地下1階は、通称「兜倶楽部」と呼ばれる記者クラブ。新聞、テレビなど約30社の記者たちが、ワンフロアを独占する。
だが1月下旬、その兜倶楽部に詰める記者たちの間で、「この記事、どこかで見たことなかった?」との質問が飛び交ったことは、あまり知られていないようだ。
その記事とは、1月26日に日本経済新聞が掲載したものになる。企業情報を扱う17面の囲み記事。見出しは「新規公開企業下方修正相次ぐ」だ。
「2016年に上場した83社中、10社が業績見通しを引き下げた」という事実を提示し、「いわゆる上場したことがゴール」という企業が増加していると指摘。「IPO(新規公開株)の信頼向上はまだ道半ば」だと警鐘を鳴らした。
記者名が入った署名原稿。1200字を超える渾身の大作だ。気合が漲っているのは一目瞭然。内容も「社会の木鐸」たる新聞に相応しいだろう。
ところが、これを読み終えた他社の記者たちは「既視感」を覚えた。ある記者はこのことを市場関係者に尋ねると答えはすぐ返ってきた。
「あー、それね……。『市況かぶ全力2階建て』で見ましたよ」
何と、日経が盗作記事を掲載したのだろうか。
■―――――――――――――――――――― 【写真】バーチャレスク・コンサルティング社の公式サイトより
(http://www.virtualex.co.jp/)
■――――――――――――――――――――
まとめサイト「市況かぶ全力2階建て」だが、市場関係者の間では群を抜いて話題になる人気を誇る。
(http://kabumatome.doorblog.jp/)
ツイッターなどに投稿された市場の話をタイムリーに、そしてウィットに富んだタイトルで掲載しているためだ。
その「市況かぶ」が1月16日に掲載した記事が興味深い。
前日15日、コールセンターの運営委託などを手がけるバーチャレスク・コンサルティング(東京都港区虎ノ門)が下方修正したことを受け、「2016年IPO企業の上場(1年以内)ゴールは10社目に」と皮肉ったのだ。
と、ここまで来ると、大半の読者はお気づきになっただろう。日経の「上場ゴール」を憂う記事と同じ内容なのだ。当然ながら、「下方修正10社」の顔ぶれは日経でも、市況かぶでも変わらない。
更に致命的なことは、日経は26日の掲載。一方、市況かぶは16日だ。こうなると、嫌が応でも盗作疑惑が囁かれても仕方ない。少なくとも「ネットの後追い記事」を疑われるのは必然だ。
ところが、更に興味深いことが続く。
上にある通り、日経が「ネット後追い」疑惑記事を掲載したのは26日。その前日25日午後3時27分、日経は、東証1部に上場しているLINE(渋谷区渋谷)の決算要約を報じる記事作成に際し、人間の記者を使わず、AI(人工知能)に〝執筆〟させたのだ。
あくまでも要約記事だとはいえ、LINEの決算が東証の適時情報開示閲覧サービス(TDnet)に載ってからわずか2分後に掲載されている。
こんなことが可能になったのは、徳島大学発のベンチャー「言語理解研究所」と東京大学松尾豊研究室と共同で開発したAIシステムを使ったためだ。
日経ビジネスではそれを「画期的」と称し、担当部署の言葉を紹介している。
それによると、「これからは入力だけで書きあげることができるような単純記事はAIで行い、記者は本来やるべき仕事に集中してもらう」と担当セクションが述べている。
その言やよし。
兜町倶楽部の記者は今のところ、盗作とまでは認定していないようだ。だが、「集中した成果が、後追い記事かよ」と苦笑している。いや、それどころか、「本来やるべき仕事に集中している日経の記者は次、どのネット記事を後追いするのだろうか」と楽しみにしているのだという。
(無料記事・了)
2017年1月4日
【無料記事】「安倍政権ブレーンの横顔」ルサンチマンの「山内昌之」

あまりに密やかで、全く目立たないが、第2次安倍政権でにわかに存在感を増している、1人の男がいる。
歴史学者の山内昌之氏だ。メディアは2016年、「東大名誉教授」と「明治大学特任教授」の肩書を使った。
東大退官は2012年。それから政権中枢への食い込みは、〝御用学者〟などというレベルを越えた。政財界どころか、日本内外でも、他に追随する人物はいない。
「スパークリングワインで」──。
山内氏と打ち合わせを希望する者には必ず、こう言われるのだという。仕事となれば、まずは腹にワインを流し込むわけだ。 ■―――――――――――――――――――― 【筆者】下赤坂三郎 【写真】山内昌之氏公式サイトより
(http://yamauchi-masayuki.jp/)
■――――――――――――――――――――
言わずと知れた、国際関係史の研究者。特に中東・イスラム地域研究の専門家だ。その博覧強記はあまりに有名だが、それだけではない。学究肌には珍しく、実地での見聞も加味され、だからこそ言説は非常に強い説得力を纏う。
ところで山内氏の自宅はどこに所在するか、ご存じだろうか。
学者といっても、紋切り型のイメージと現実は異なり、例えば田園調布や鎌倉に住む者は少ない。大半の住所は府中、三鷹、吉祥寺といったところで──我々、平凡な会社員と同じように──郊外の沿線から勤務先の大学へ通っている。
それが山内氏の場合、何と赤坂8丁目だ。近くにはカンボジア大使館が建ち、赤坂5丁目のTBS本社も、六本木の東京ミッドタウンも指呼の間。いくら東大とはいえ、赤坂に居を構えている学者など見たことも聞いたこともない。
一体全体、山内氏の懐具合は、どうなっているのだろうか。
山内氏は現在、フジテレビ特別顧問と、三菱商事顧問に就いている。週に2日はフジテレビ、他の2日は三菱商事、そして残る1日は明治大学に出勤する。いやはや、「元東大教授」らしからぬ多忙で、華やかな印象の毎日だ。
少なくとも三菱商事では、専用車も準備されている。自宅から出て颯爽と最新型クラウンの後部座席に乗り込む姿は、東大名誉教授というよりは、三菱商事アメリカ支社長と言ったほうがしっくりくる。
そんな山内氏は1947年、国鉄労組の父親のもと、札幌市に生まれている。
本人も北海道大学に進学してからは学生運動に身を投じた。所属はブントだという。絵に描いたような「団塊の世代」(1947〜49年生れ)と形容していいだろう。
ご存じの通り、この時期に学生運動からの転向したグループは、社会に出ると一気に権力志向へ突き進むケースが少なくない。
本来、東大教授の退官本流は、放送大学なのだ。私大への教授職が用意されても、放送大学教授を兼任するということもある。
東大を退官してから、フジテレビと三菱商事の顧問室に直行した学者は、どう考えても山内氏が嚆矢に違いない。もとより東大時代から、メディア露出の好きな学者だとは思われていた。柔らかい語り口に加え、ビジネスマンのようなスマートさも兼ね備える。能力が桁違いなのは言うまでもない。だからこそのフジテレビ、三菱商事の招聘だったはずだ。
そんな山内氏は意外なことに、ことあるごとに東大批判を繰り返す。その言説の中心は「東大には東大教授になりたい病(の人間が)多い」というものだ。教授になるまでは刻苦勉励を続けるが、その夢を果たした途端、何も勉強しなくなるのだという。
しかしながら、ポストを得ると勉強しなくなるのは、日本全国の大学教授に当てはまる。別に東大に限った話ではなく、単なる一般論だ。山内氏の母校、北海道大学でも類例は掃いて捨てるほどあるだろう。
山内氏の頭脳、見識を考えれば驚くほど、指摘に鋭さや深みに欠ける。
東大内部にいたのだから、リアルな現状を語ってくれれば、それだけでいいのだ。なのに、そうした「内部告発性」にも乏しい。失礼を承知で言えば、新橋の居酒屋でエリート東大生を批判して悦に入る酔っ払いの戯言と大差ないのだ。
いずれにしても、山内氏が東大に愛着を持っていないことだけは確かだろう。東大における「比較政治」の本流はやはり、94年に東大大学院・法学政治学研究科教授となり、13年に定年退職となった塩川伸明氏なのだ。
塩川氏と異なり、山内氏は東大法学部に講座を持つことが叶わなかった。これだけで傍流が認定されてしまうわけだが、そうした〝本流〟の塩川氏と、〝傍流〟の山内氏は、東大で〝覇権〟を争った。ところが、この2人、相当に似た経歴の持主だということが、更に話をややこしくする。
先に見たとおり山内氏は47年生まれで、一方の塩川氏は48年。塩川氏は都立日比谷高から東大に進学し、やはり山内氏と同じように学生運動に身を投じた。山内氏がブントだったのに対し、塩川氏は中核派だったという。
山内氏がイスラム、塩川氏はロシア政治と、表向きの専門分野は異なる。だが、ロシアはイスラム系民族色の強い国、となると、この2人の因縁はより鮮明さを増す。山内氏もイスラムを通じてロシアを見ていたのだ。
これほどの碩学が、同じ大学で覇を競い、結果として東大生え抜きの塩川氏が本講座を持ち、北大出身の〝外様〟である山内氏は〝疎外〟された──となれば、山内氏は様々な局面で鬱積したものを抱え込まざるを得なかっただろう。
そして山内氏は傍流のまま、野に放たれた。まさか「在野の研究家」になるはずもなく、「野に遺賢なし」を自ら証明しようとしたのか、安倍政権の内部に深く食い込んだ。
今や山内氏は安倍政権における安全保障分野の主要ブレーンと言っていい。肩書の1例としては、内閣国家安全保障局の顧問を務めている。また2016年9月には、特に注目されている「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」のメンバーにも選ばれた。
東大時代のルサンチマンを晴らすため、山内氏は安倍政権の枢要へ、どんどん突き進んでいくのである。
2016年12月12日
浅田舞に「連盟激怒」で「出入り禁止」の驚愕情報

フィギュアスケートの浅田真央(26)の姉で、自身も元選手でタレントの浅田舞(28)が、競技大会などに「出禁」=出入り禁止になるという驚愕情報が飛び込んできた。
フィギュアの実力では妹に遠く及ばなかったものの、抜群のスタイルと美貌でスポーツキャスター、タレント、グラビアと幅広く活動する舞に一体何があったのか――。 ■―――――――――――――――――――― 【記事の文字数】1100字 【写真】浅田舞公式サイトより (http://mai-asada.jp/)
■――――――――――――――――――――
» Read more
2016年11月21日
【完全無料記事】「Bリーグ」真の実力は「世界40位以下」

(※この記事は完全無料です。会員登録は必要なく、末尾の「了」で記事は終わります) 男子バスケットボールのプロリーグであるBリーグが開幕した。特筆すべきは、やはり床一面にLEDが敷き詰められた鮮やかなコートだろうか。CGが投射されると美しい映像が自由自在に踊り、ゲームの演出としてはトップクラスといっても過言ではない。観客の感動に大きな貢献を果たした。 ハーフタイムのショーも善戦しており、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスによる開幕戦は満員。リーグ発足の第一功労者であるバスケットボール協会前会長の川淵三郎氏も「90点」と高評価を与えた。 しかし……。 フジテレビ系列がゴールデンタイムで中継した開幕戦の平均視聴率は5・3%(関東地区)。これでは放映継続は不可能だろう。しかも、開幕戦で露呈したのは、「競技そのものの実力不足」(関係者)だった。 「要所での得点は外国人選手ばかり。双方で連続してフリースローを外し続ける失態もあり、目を覆わんばかりの実力だった」(同) どれだけ派手な演出を前面に押しだしても、リアルな実力は隠しようがない。 同じ川淵氏がチェアマンとして発足させた、Jリーグの開幕時には、盛りは過ぎたとはいえ、ジーコ(鹿島アントラーズ)、ゲーリー・リネカー(名古屋グランパスエイト)、ラモン・ディアス(横浜マリノス)……といった世界のスターが集結していた。 更に重要なのは、その後も継続してドラガン・ストイコビッチ(名古屋グランパスエイト)、ドゥンガ(ジュビロ磐田)、レオナルド・ナシメント・ジ・アラウージョ(鹿島アントラーズ)ら実力選手がピッチでレベルの高いプレーを繰り広げ、文字通り日本サッカーの実力を底上げしたことは特筆に値する。 だがBリーグには客を呼べる外国人選手も招聘できなかった。別の関係者は「日本バスケの実力を冷静に考えれば、これこそが最大のアキレス腱だ」と頭を抱える。 「Bリーグの開幕直前、イランで国際大会『2016 FIBAアジアチャレンジ』が開催されたのだが、日本代表は初戦で韓国に73-80で敗戦。2次ラウンドでも地元のイランに57-68で敗れた。かろうじて進んだ準々決勝でもヨルダンに80-87で敗退。日本はアジアの6位で大会を終えたという体たらくだった」 これがリアルな実力だとはいえ、問題はスポーツ紙などのスポーツジャーナリズムが大会の惨敗を報じていないことだ。もしサッカーの日本代表が、これだけの大敗を喫すれば、一般紙やテレビを含む大手メディアであっても黙ってはいないだろう。 むしろ常に善戦しているのは女子バスケだ。世界で15位にランクされ、上位国とも好勝負を演じている。だが男子は世界の48~49位あたりを定位置とし、アジアですらお世辞にも上位国とはいえない。その実力が、そのままBリーグにも反映されているというわけだ。別の関係者は「このままでは2020年東京五輪の開催国枠だって危ないですよ」と言い放つ。こうした現状を知るほどBリーグの派手な演出が、白々しくしか映らないのである(了) ■―――――――――――――――――――― 【写真】攻め込む琉球・喜多川修平(中央)=(開幕戦・国立代々木競技場・撮影:産経新聞社)
■――――――――――――――――――――
2016年9月26日
週刊文春「新谷編集長」人事怪情報の「出所」
2016年9月20日
【無料】Jリーグ&英パフォーム「2100億」契約に意外盲点

Jリーグが、イギリスの動画配信大手・パフォームグループと2017年からの10年間で、何と総額2100億円の放映権契約を結んだことは大きな話題として報じられた。年間ベースの場合、スカパーJSAT株式会社などと締結する現行契約の約7倍に跳ね上がるという。だが関係筋は「この額に見合う魅力あるコンテンツをJリーグは提供できる能力があるだろうか」と懸念を打ち明ける。
■―――――――――――――――――――― 【購読記事の文字数】 【写真】DAZN(ダ・ゾーン)公式サイトより
(https://www.dazn.com/ja-JP)
■――――――――――――――――――――
» Read more